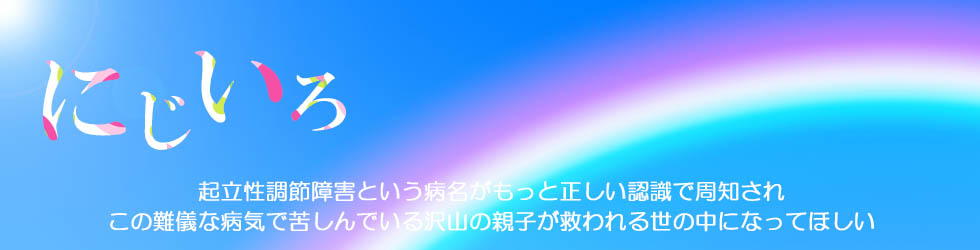胃腸が弱ってる人、炎症を起こしている人、何らかの原因で消化能力が落ちている人にとって、助っ人になってくれるのが塩麴と醤油麹。
我が家では、買ってきたお肉やお魚は塩麴や醤油麹に漬け込んでから冷凍するようにしていますので、これはもう必須アイテムになっています。
弱っている胃腸をサポートをしてくれる麹菌
麹とは、米や麦、大豆などの穀物を麹菌と言われる菌を使って発酵させたものです。
この麹が持っている「プロテアーゼ」と呼ばれる消化酵素には、肉のタンパク質を分解してくれる働きがあるので、お肉やお魚を塩麹や醤油麹に漬け込む事により、タンパク質の分子の結びつきが弱くなり、柔らかいお肉に仕上げてくれるんです。
さらに、そこから糖やアミノ酸を生成し、体が消化吸収しやすい状態にしてくれるので、すでに半分ほどは食材が分解されているということになるので、消化に使うエネルギーは半分で済むということ。
自律神経の働きが弱くなっている、起立性調節障害の子ども達にとっては、消化吸収を助けてくれる塩麴や醤油麹の存在は欠かせないものとなりました。
他にもあります塩麴・醤油麹の嬉しい効果
麹には消化吸収を助けてくれる以外にも、沢山の嬉しい効果があります。
何より感じているのは、
「食材を美味しく変化させること」
麹が持っている微生物が食材本来のうま味を引き出してくれるので、旨味が格段に上がり柔らかい質感になるので、どのお料理もグレードアップしちゃいます![]()
こうした発酵調味料を使う事で腸内環境が整えられていくので、書ききれないくらい沢山の効果があるんです。
- 代謝アップ
- 免疫力アップ
- 抗酸化作用
- 疲労回復
- 便秘予防
- 美肌効果
- 動脈硬化の予防
- GABAによるストレス緩和
- イライラの緩和
- 高血圧の予防
- 中性脂肪の抑制
- メラニンの抑制
などなど。いい事づくめですよね。
塩麹の作り方

<材 料>
- 米麹 200g (乾燥麹)
- 天然塩 70g
- 水200g
<作り方>
1. ぬるま湯に天然塩を混ぜて溶かす。
(塩が全部溶け切らなくても大丈夫)
このあと米麹を混ぜるので、麹菌が死滅しないよう熱湯ではなくぬるま湯にしています。
熱湯で天然塩を溶かした場合は、ぬるま湯になるまでおいてから、2.に進んでください。
2. 1.に米麹を混ぜる。
塩分の量はレシピサイトで様々な分量が書かれていますが、麹屋さんのホームページに、「米麹に対して塩分の分量は35%がベスト!」と書かれていたので、私はいつもこの分量で作っています。
塩分控えめで作ってしまうと腐敗の原因になってしまうそうなので、ここでは減塩せず、お料理する時に加減すれば良いと思います。
3. 清潔な保存容器に移し、常温で1~2週間くらい熟成。
熟成期間中は、毎日1回スプーンで混ぜて空気を入れ込んであげます。
熟成期間は季節によってまちまちですので、麹の芯がなくなって、おかゆみたいになるまで常温で見守ってあげてください。
4. おかゆのようなとろみがついてきたら、冷蔵庫へ移動して保管。
冷蔵庫で保管後も少しずつ熟成は進んでいきますので、麹と水が分離してきたら、その都度混ぜるようにしてください。半年くらいで使い切りましょう。
醤油麹の作り方

なんと、醤油麹はうま味成分のグルタミン酸が、塩麴の10倍以上![]()
しかも塩麴より簡単です![]()
<材 料>
- 米麹 200g (乾燥麹)
- 醤油 200g
<作り方>
1. 米麹と同量の醤油を混ぜるだけ
2. 清潔な保存容器に移し、常温で1~2週間くらい熟成。
熟成期間中は、毎日1回スプーンで混ぜて空気を入れ込んであげます。
熟成期間は季節によってまちまちですので、麹の芯がなくなって、おかゆみたいになるまで常温で見守ってあげてください。
3. おかゆのようなとろみがついてきたら、冷蔵庫へ移動して保管。
冷蔵庫で保管後も少しずつ熟成は進んでいきますので、麹と水が分離してきたら、その都度混ぜるようにしてください。半年くらいで使い切りましょう。

熟成途中で白くカビみたいな物が出来ても、それは産膜酵母(さんまくこうぼ)と呼ばれている酵母菌なので大丈夫。スプーンで混ぜ混ぜしてあげてください。
注)青いカビは絶対ダメ。捨ててくださいね。
ワンポイント
塩麴も醤油麹も、ブレンダーでペースト状にしてあげると、より使いやすく便利になります。液状にする事で、そのままお醤油の代わりになったり、ドレッシングにした時にも馴染みやすくなるのでおススメ。
酵素が素材を柔らかくしてくれるので、パサつきがちな鶏むね肉を漬け込んで鶏ハム作ると、ふっくら柔らかくて美味しくなるので、我が家ではしょっちゅう作り置きしています。
いかがでしたか?
今まで使っていたお塩と醤油を塩麴と醤油麹にするだけで、美味しくなって、栄養を吸収しながら胃腸の負担を軽くする事が出来るなんて、一石二鳥ですよね![]()
![]() 忙しい人はこれね。
忙しい人はこれね。